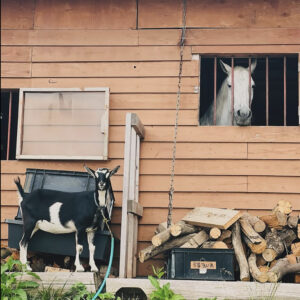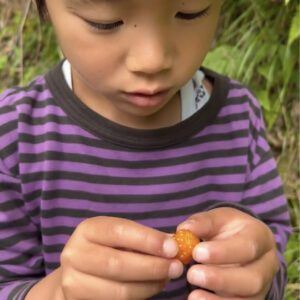園長のコラム②

森のちから こどものちから
~園長熊谷の呟きコラム~

【2014.8月号】
今年の夏は曇りがちで涼しい日が続き、もう秋?といった速さで夏休みが終わってしまいましたね。
残暑もなく、とても過ごしやすい気温が続いています。お散歩にはとても最適な温度なので、長い距離を意識しながら体力をつけていっています。この時期にしか行けない、その季節を楽しめるフィールドに極力行きたいと思います。
10月の後半に那岐山登山登山に行きます。春から少しずつつけていった体力がどれだけついたか、そして自分に自信をつけることも目的としています。11人という子ども達の関わりが、お互いをどう確かめ合って目標を達成してゆくのか。登山と言う大きな目標を終え子ども達の中に何が芽生えるのか…。秋の深まりと共に、子ども達の心の深まりを確かめることができたら意味のある登山になるのではないか、と思います。その為にも、小人数では意識しにくい年齢の差をもっと子ども達が自覚し「自分よりも小さい子だから手伝ってあげよう」とか「年長になったらあんなことができるようになりたい」という、気遣いや憧れを持った関わりができるよになって欲しい、というのが狙いでもあります。
朝の会では子ども達がみんなの前で意見を述べ、人の話も聞くように仕向けています。まだ、話すこと、聞くことが難しい子が多いなかで`年長としての役割′をしっかりと育ててゆきたいと考えます。保護者さんにも、日々ローテーションを組んで保育の場を体験して頂いておりますが、気付いた点や思うことをいろいろと聞かせていただきたいと思います。
さて今回のテーマは‘叱る’について自分自身考えてみたいな~と思いました。「最近怒りすぎかも・・・」「子どもが挙動不審なのは、私がすぐ叱っちゃうからかも・・・」と思われる方もおられるかもしれません。言うことを聞かない3人の男の子を持つ私は、サザエさんのように拳を振り回しながら追いかける逞しい女になってしまいました。怒りすぎて疲れ果てて、家出しようかと何度思ったことか・・・。ふと、「そうか…。怒るから疲れるのか。怒らないように考え方を変えてみるのもいいかも」なんて心に決めた時期もありました。自分が疲れない子育て方法を生み出す事も大切ですよね。
‘怒る’と`叱る‘とでは意味が違います。皆さんの中でもシュタイナーや教育本などで叱ることの技術を勉強されている方もいらっしゃると思います。でも、分かってはいるけど・・・と、なかなか思うようにはいかないのが子育て。感情に任せて怒ってはいけないし、きちんと子どもに伝わるように説明しなければいけませんよね。
私の場合ですが、幼児と児童では叱り方の本気度が違うな~と感じることがありました。幼児は分かっているようでいない気がして感情的になってはいけないな~と徹底的には怒れませんでした。小学生だと分かっていてわざとやっているので、心底腹が立ちます。(うちの子の場合だけかもしれませんが…)これがまた思春期だと、もっと難しい!本気であんたのことを想って怒っているんだぞ、という気持ちで対応しないと逆効果、プンプン反抗するだけで問題解決には至りません。
すぎぼっくりでは、子ども同士の喧嘩も止めることはしませんし、ある程度のいたずらの良し悪しの判断も子どもに任せます。が、命や怪我に関わることは別です。石を人に向けて投げた場合、命に関わる怪我があってはいけません。また、怪我を負わせた方にも心に傷が残ります。そのようなことにならない為にも良い事と悪い事をはっきりと自覚させなければいけませんね。子どもがわざと人に石を投げたりすれば、真剣に向き合って叱ります。感情的にならず、なぜいけないことであるのかをしっかり伝える大人が近くにいることはとても大切なことだと思います。 叱ることを通じて‘いつも君の事をしっかりと見ているんだよ。そして、君の事が大切だからこそ真剣に向き合っているんだよ’という気持ちを伝える為にも時には厳しく叱ることも重要なんだと思います。また叱り方も年齢、気質によって使い分けなければ、同じ叱り方でも逆効果なんてこともあります。
すぎぼっくりのもう一つの叱り方、それは子どもが子どもを叱ることです。大人がすぐに関与しないと、子どもがその問題に対処してくれます。例えば、石を投げて遊んでいた年少児がいました。エスカレートして近くにいた子に当たってしまいました。ごめんもいえなくて固まっていると、とっさに年中児が「~ちゃんに石が当ったで!ちゃんとごめんなさいしないと駄目でしょ!人に当らないようにせんといけんで!」としっかりと伝えているではないですか!大人が言うよりしっかりと心に響いていたようで、「ごめんね~」と反省した様子でした。自分達でしっかりと問題を解決させる力を持っているんですよね。ちょっと胸が熱くなったワンシーンでした。
タグ
-
URLをコピーしました!